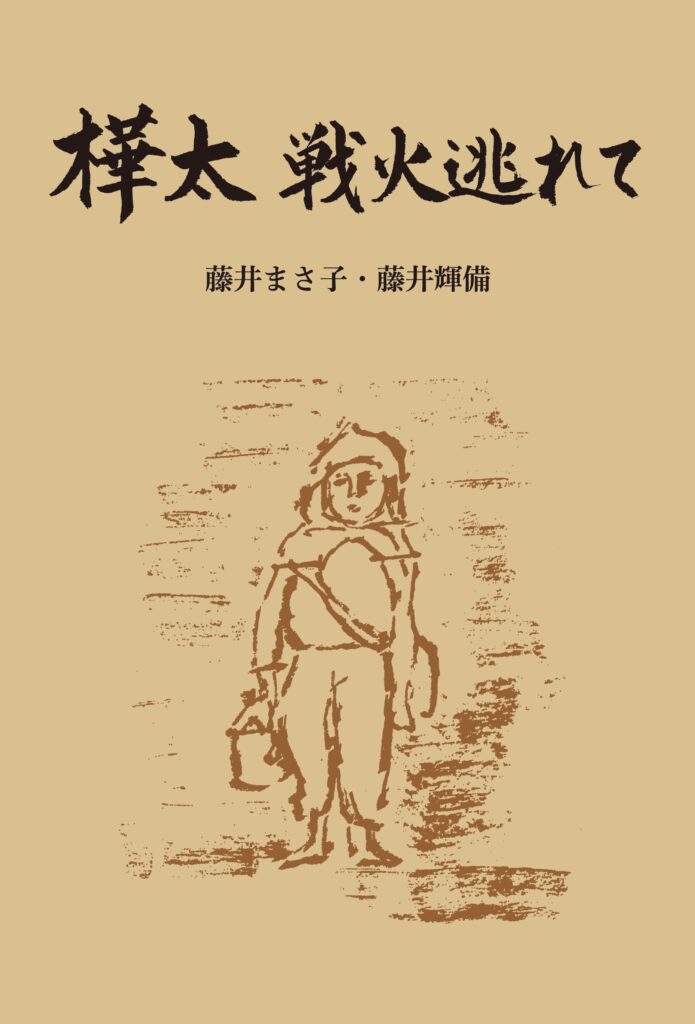出版に際して
四十年以上前、ガリ版刷りで『最涯の島』を読んでいた。
葦の会会報と文集『渓流』に三年にわたって連載され、その連載中に十数名で藤井輝備先生の故郷利尻島を訪ねた。岬の番屋跡はわずかに石塁が残るのみで、先生は真夏の風に吹かれ佇んでおられた。一族の眠る無縫塔に手をあわせ、北見富士神社に参詣し松蔵の写真を見た。作品完結の四年後、お孫さん三人をまじえた旅行を企画し、数人で利尻を再訪している。
それからかなりの時間が流れ、葦の会は五十年誌を作ることになった。執筆にあたり著者のガリ版刷り全作品集に目を通し、『最涯の島』は一冊の本として後世に遺すべきだと思った。
これは、明治半ばから大正末にかけてのニシン漁黄金期の話である。数日の稼ぎで一年が暮らせるほどの莫大な利益を生み出すニシンは、「魚に非ず米にも匹敵する貴重な魚」だと「鯡」の文字があてられた。いま北海道日本海側沿岸に、往時を伝える鰊御殿が遺されている。
島は当時和人千人アイヌ千人が住む無法地帯で、アイヌは漁獲のほとんどをただ同然に買いたたかれるなどの差別を受けていた。幕末、明治の大転換期はそう遠くない頃で、弁財とよばれる北前船が港々を巡って交易をしていた時代の北の離島が舞台である。
佐渡を出た巨漢の松蔵が、弁財船や行商、警邏 を経てニシン漁網元として活躍するさまは、大河のごとき一族の物語だ。みな縁あって「はちの」の岬に身を寄せ、懸命に生き、ある者は別れ、ある者は死んでゆく。生きることの輝きとはかなさに温かい眼差しを注いでいる。母親との縁薄く祖父母に溺愛されて育った藤井先生は、幼少期を過ごした利尻島での暮らしを愛惜の情をもってつぶさに描き出している。図らずもそれはその時代、その土地の暮らしの文化を映した貴重な作品となった。ニシン群来の大漁となれば、学校は休みとなって、島あげての活気の渦が起こる。保存技術がない時代なので、夜通しぶっ続けの作業が何日も続く。番屋を根城に生きた人たちの汗や涙の物語は漁業文化も伝えている。
先生は自著『たまゆら』で、「私は常々、幾重にも虚偽に粉飾された官製の国史よりも、庶民の手に成る一家の歴史の方が、はるかに価値が高いと申してきました。そんな思いもあって、『最涯の島』というものを書きました。それは『はちの』という私の育った漁場の屋号を主人公にした一族の人間模様でした」と語っている。
また、『孤愁』では、「利尻の昆布の解禁日(八月五日頃)に間に合うように帰省するのが恒例である。日本海側を北上して小樽まで行き、そこから汽船に乗るのであった。海路十八時間で沓形に着く。私の採る昆布だけで、一年分の授業料は充分であった」と書いておられる。
一九六〇年創立の葦の会は女性の学習サークルで、千葉県茂原の地に誕生した。自分の人生の主人公になろうと呼びかけられ、人間尊重を学び、思考、実践、自己表現をめざした。また広い視野を持ち、本質をみる目を育てようと励んだ。自己成長をはかって切磋琢磨し合う会である。藤井先生は創立当初から亡くなられる一九九三年まで、ずっと助言者であり指導者であった。
著作の中から、人生観の一端にふれているものを紹介したい。
「〝なつかしい人になれ、なつかしい人をもて〟と私はよく言います。これが最高の友情だと思います。〝恋〟も〝愛〟も両性間では美しいのですが、激情と狂気の要素が強くて、継続して育てなければ必ず色褪せて来ます。〝なつかしさ〟は少し相互に距離をもちますが、崩れないし変色もしません。これが人間の結びつきとしての最高のものでしょう」(『たまゆら』より)
葦の会は二〇一七年十二月をもって、五十七年十カ月の活動を終えた。自前の会館の土地・建物を売却し、すべてを社会的還元のもと五カ所に寄付をした。その一環としてこの本を上梓する。